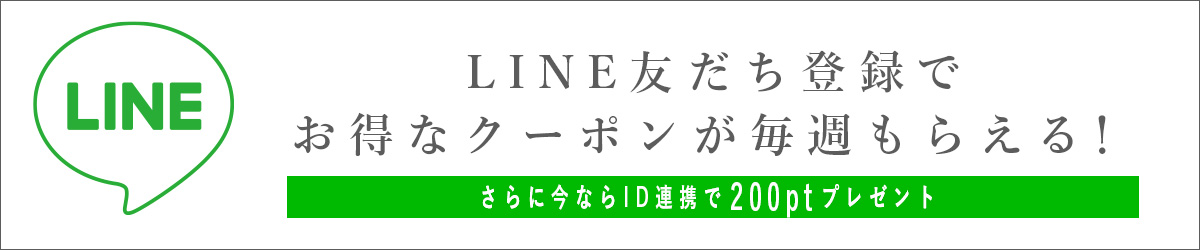伝統的な馬の駆け比べ!上賀茂神社の葵祭に行ってみませんか?

毎年5月に京都で行われる「葵祭」。
「祇園祭」や「時代祭」とともに「京都三大祭」と呼ばれています。
葵祭は古代から受け継がれてきた由緒あるお祭りです。
時代とともに姿を少しずつ変えながらも、古の祭を現代に伝えています。
今回は葵祭の歴史や葵祭と馬との関係についてなどを紹介します。
この記事で分かること
・葵祭の歴史
・賀茂競馬(かもくらべうま)とは?
・上賀茂神社の神馬の出社日は?
上賀茂神社 葵祭とは?
葵祭は毎年5月15日に行われる上賀茂神社と下賀茂神社の例祭です。
平安時代の衣装に葵の飾りをつけた行列が京都御所から下賀茂神社を経由し、上賀茂神社まで練り歩きます。
正式には「賀茂祭」と言いますが、牛や馬も含めた行列の全員がフタバアオイの飾りを身に着けていることから、葵祭と呼ばれるようになりました。
行列の当日のみならず、前儀が両神社で5月初頭から行われます。
葵祭の歴史

時は6世紀。第29代欽明天皇の時代に凶作による飢餓に見舞われてしまいます。
欽明天皇は「鴨の神」に勅使を送り、例祭を行うことにしました。
これが現代の葵祭の起源と言われています。
そのため、葵祭は上賀茂神と下賀茂神社に送った勅使が天皇の祝詞やお供えを奉納するのが目的です。
平安時代に京都で祭と言えば葵祭を指すものだったのが、室町時代になると衰退し、一度は姿を消してしまいます。
江戸時代に復活するものの、明治維新のころにまた消えてしまいます。
その後、明治17年には復活しますが、第二次大戦で縮小せざるを得ない状況に追い込まれてしまいます。
戦後は行列の巡行も再開されて、現在の形に収まりました。
葵祭の開催時期

葵祭は毎年5月15日に開催されます。
5月15日の午前10時半ごろに京都御所を出発する行列が下賀茂神社と上賀茂神社まで巡行します。
しかし、葵祭には行列の巡行が行われる5月15日以前にたくさんの前儀が両神社で行われており、その中には馬にまつわる神事がいくつかあります。
5月初頭に行われる賀茂競馬足汰式(かもくらべうまあしぞろえしき)から、行列の数日前に行われる御蔭祭(みかげまつり)まで多種多様な前儀が5月15日の行列に向けて、祭の雰囲気を少しずつ盛り上げていくのです。
賀茂競馬(かもくらべうま)について

その神事の中でも人気なのが賀茂競馬(かもくらべうま)。
天下泰平と五穀豊穣を祈って行われていた、古式の宮中競馬が神社に場所を移して行われています。
寛治7(1093)年に宮中競馬を上賀茂神社で奉納をしたことを起源にしていると言われています。
菖蒲根合わせ、必勝祈願の奉幣の儀など競馬会の儀を行った後に2騎1組の計5回の競馬が行われます。
吉田兼好著の随筆「徒然草」にも記述があり、古式の競馬を現在に伝えていると言われています。
足利義満や織田信長などの武将たちも賀茂競馬を観覧をしたと伝わっています。
賀茂競馬のルール
直線約400メートルの馬場で、右方(うかた)と左方(さかた)の2頭に約1馬身の差をつけて競走させます。
その差が「勝負の楓」の木のあたりで、広がっていれば前方の馬の勝ち、差が縮まっていれば後方の馬の勝ちとします。
左方が勝てば赤い扇、右方が勝てば青い扇、同着の場合は両方の扇が広げられ、勝敗が乗尻に伝えられます。
また、競馬が行われる前に馬の能力を図り、出走の順番を決める「賀茂競馬足汰式(かもくらべうまあしぞろえしき)」が行われます。
馬の健康状態や乗尻(騎手)の技量なども考慮し、組み合わせや発走順が確定します。
一ノ鳥居(南)から本殿側(北)に向かって1頭ずつ走ったのちに、2頭併せで試走します。
賀茂競馬の楽しみ方や見どころ

賀茂競馬では、スタートの合図が乗尻の冠合わせで行われます。
冠合わせとは、乗尻がお互いに顔をあわせ、スタートのタイミングを図ること。
乗尻は自分に合ったタイミングでスタートを切りたいため、なかなか相手とのタイミングは合いません。
ここから勝負の駆け引きは始まっているんですよ。
冠合わせでスタートが切られ、競馬が始まると「むちうちの桜」のあたりで、乗尻が声を挙げて鞭を入れると、馬が加速していきます。
むちうちの桜以降の馬場周辺では、さらに迫力をました馬の走りを見ることができます。
乗尻の衣装にも注目です。
足汰式では烏帽子に浄衣の装束、本番の競馬では舞楽装束を身に着けています。
当時の競馬の正装だと言われているんです。
神馬(しんめ)に会いたい!神馬の出社日は?

上賀茂神社には神馬舎があり、代々白い馬を神馬として迎えています。
現在の神馬は戦後七代目の神山(こうやま)号。
六代目が20歳になったことから、もともとは競走馬だったマンインザムーンを2021年に神山号として新たにお迎えしています。
普段は近くの大学の厩舎におり、毎日出社しているわけではありません。
祭礼の日や祝日に会えます

基本的には日曜、祝日、祭典日の9時〜15時ごろに神馬舎で会えるようですが、神山号の体調によっては変更されることもあります。
神山号は普段は京都産業大学馬術部の厩舎にて大切にお世話されており、出社日には馬運車で出社します。
大学の厩舎から曳いて出社しようとしたら、暴れて大変だったので馬運車を購入した経緯があるそうですよ。
現在は新しい生活にも慣れて今はかなりおとなしくなったのだとか。
1月7日には「白馬奏覧神事(はくばそうらんしんじ)」が行われます。
年始に白馬を見ると邪気が払われるという故事に則って行われていた宮中行事を神事化したもので、毎年行われています。
当日は神前に神馬を供する儀式である御馬飼の儀が行われます。
また、正午、13時、14時、15時には牽馬の儀も行われます。
牽馬の儀では神馬が神前でお辞儀をする様子が参拝客を和ませているそうです。
神山号は元競走馬ではありますが、現在は神様にお勤めしているため、賀茂競馬には参加していません。
参拝者は神馬にニンジンをあげられることも!
神山号が出社している際は神社が準備したニンジンをあげられることもあります。
神山号も参拝者からのニンジンをとても楽しみにしている様子だそうです。
ニンジンをあげたら、ご利益があるかもしれません!
まとめ

今回は京都の葵祭についてご紹介しました。
葵祭の前儀には、ここで紹介した賀茂競馬以外に流鏑馬の奉納もあります。
また、行列には牛も馬も参加しています。
機会があれば、葵祭や上賀茂神社に是非、お出かけください。
このページをシェアする