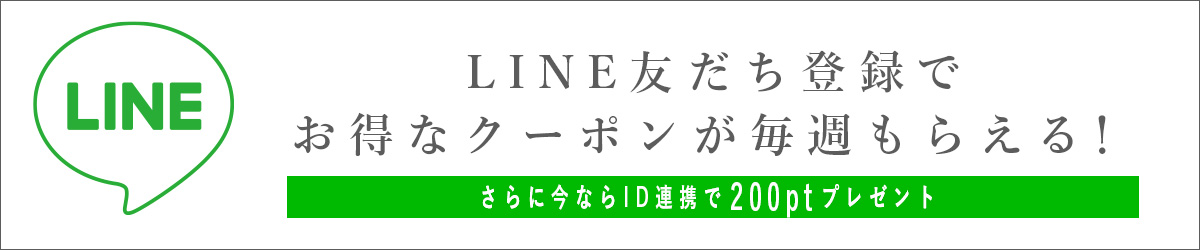馬好きなら学びたい!馬の体の仕組み・生態について

馬が好きになるともっと馬のことを知りたくなりますよね。
今回は馬の体や生態について深掘りします。
馬は人間のこともよく観察しており、私たちの感情もある程度は察していると言われています。
馬の生態を理解して、人間も馬もお互い快適に過ごせるようにしていきたいですね。
この記事で分かること
・馬の生態って?
・馬の体の特徴や仕組みについて
馬ってどんな動物?

馬の祖先は森に住んでいる小型の四足動物でした。
最古の祖先はヒラコテリウム(エオヒップス)。
約5000万年ごろにはすでに誕生して北米の森に住んでいました。体高は柴犬ほどでした。
その後、気候の変化により、住処を森林から草原に変えます。
草原では森のように身を隠す場所がなかったため、天敵から身を守り、生き残るすべとして速く走れるように馬は進化を遂げてきました。
たとえば、足には指がありましたが、速く走れるように中指だけが蹄に進化をして、他の指は退化していきました。
また、自然界では1頭のオスを中心に形成したハーレムにて生活をしますが、休むときも、群れから必ず1頭は見張り役を立てます。
見張り役は危険に気づいたら、すぐに合図をして逃げるように促します。
このように群れを形成して生き残ってきた馬はコミュニケーション能力や社会性の高い動物です。
最近の研究では表情などから人間の感情もある程度、察することができると言われています。
実はこれにも理由があります。
何世紀にもわたって生き残ってきた馬の祖先ですが、あるとき、人間に乱獲されるなどの理由で絶滅の危機を迎えます。
そこで、馬が決断したのは「人間と一緒に暮らすこと」。その結果、馬は家畜化されて、純粋な野生種は絶滅しました。
現在の野生馬は、家畜化されたものが逃げ出して自然の環境下で暮らした個体の子孫だと言われています。
こういったことから、人間と馬には互いに手を取り合って生き残ってきたという歴史があり、切っても切れない関係にあります。
関連記事:
馬は実は小動物だった?馬の祖先と馬の進化について
馬の体の特徴について
そんな人間のパートナーである馬たちの体の特徴や仕組みを詳しく見ていきましょう。
耳

馬は耳を細かく動かすことができます。
なんと馬の耳の周りには13種類もの筋肉があるからなのだそうです。
もちろん、左右バラバラに動かすこともできます。
これも、いろんな角度の音を拾っていち早く危険を察知するために進化してきたためと考えられます。
馬は数キロ先の音も拾うことができると言われています。
音に敏感な馬の方が早く危険を察知できるため、敏感な馬の子孫だけが生き残ったのではないかとも言われているそうです。
音を苦手とする馬が多いのにはこういった理由もあるのかもしれませんね。
また、耳からは馬の感情を読み取ることもできます。
たとえば、緊張しているときは耳が右や左にバラバラと動いていますが、リラックスしているときは耳から力が抜けます。
気をつけなくてはいけないのは、耳を後ろ側にぺたんと倒しているとき。
このとき、馬は怒っています。咬まれてしまう可能性もあるので、耳を倒しているときはそっとしておきましょう。
たくさん動かしているからなのか、耳の根本の筋肉をマッサージしてあげると喜ぶ馬もいます。
鼻

馬のチャームポイントである鼻。鼻は生きていくうえでも、かなり重要な器官です。
馬は口では呼吸することができません。
鼻呼吸をすることしかできません。
つまり、鼻から息ができないと窒息してしまうのです。
競走馬が肺からの鼻血で競走停止になるのは、馬が呼吸困難に陥ってしまう可能性を排除するためなのです。
日本中央競馬会(JRA)では、1回目の出血で1カ月間、2回目は2カ月間、3回目からは3カ月間の出走停止期間がそれぞれ設けられています。
出走停止期間中に治癒する馬もいれば、鼻血を繰り返してしまい、引退に追い込まれてしまう馬もいます。
馬の嗅覚は人間の1000倍ともいわれており、仲間もにおいで識別することができるようです。
牡馬は、牝馬に発情が来ているかも尿のにおいで判断できます。
馬が上唇をカールさせる「フレーメン」も嗅覚に関係のある行動です。
これは、牝馬の発するホルモンなどのにおい物質をたくさん取り込むための行動で、初めて嗅いだにおいや自分の好きなにおいを嗅ぐとフレーメンする馬もいます。
とても柔らかい鼻先は人間の手のような役割も果たします。
細かく器用に動かせるので、嫌いなものが餌に入っていると鼻先を使って上手に避ける馬もいるのだそうです。
目

馬の目は人間の目の2倍ほどの大きさがあると言われています。
視野は350度です。
視野が広いのも捕食される危険から逃れるためでした。
実はもともと馬の祖先の目は犬や猫のように前方についていたのですが、草原で暮らすようになってからどの角度から敵がきても、すぐに視野に入れられるように進化の過程で目が横に動いていったのです。
横に目がついているため、両目で見ることのできる範囲は非常に狭く、距離感を掴むのが苦手なのだそう。
距離感がつかめないからこそ、できるだけ早く敵に気づいて逃げることが重要だったのですね!
馬には黄色が一番見えやすいようです。
青や緑も比較的見えやすい色だと言われていますが、赤は見えづらいようです。
自然の環境下では、暗い場所でも目が見えないと生き残れません。
そのため、発達したのがタペタム(輝板)と呼ばれる目の器官で、少ない光でも目が見えるのだそうです。
こうした目の作りの違いにより、馬は人間と同じように色が見えません。
口

馬たちはグルメです。
馬の舌には味蕾という人間の舌にもみられる味覚の受容器官がたくさんあります。
塩味も甘味も敏感に感じることができます。
馬の口の周りに生えているヒゲは神経にもつながっていて、距離感や位置、動きなどを把握することができると言われています。
特に死角になる下唇の下にはたくさん生えています。
こういったアンテナの役割を果たす馬のヒゲを整えるのはご法度。
現在では多くの国で禁止されていますが、昔はきれいに整えるべきだとされていたようです。
馬の歯は、牡馬が40本、牝馬が36本と性別によって、本数が違います。 理由は犬歯。
牡馬には犬歯が生えますが、牝馬には生えないのだそうです。
また、馬にも乳歯があり、切歯と臼歯の一部は3歳、競走馬でいうとクラシックレースを走っているころに生え変わります。
切歯と臼歯の間には歯槽間縁という歯のないスペースがあり、ここにハミを入れます。
しかし、臼歯は伸び続けるため、ハミが収まりやすいように削る必要があります。
馬の歯医者さんの主な仕事のひとつが臼歯のお手入れです。
ほかにもリラックスしていて、口が半開きになっている馬を見たことある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
唇をパクパクと鳴らして、暇つぶしをする馬もいます。
馬の感情は口にもよく表れます。
脚

すらりと細長く、速く走れる脚も馬の大きな特徴です。
肉食動物などから速く逃げられるように、進化の過程で体が大型化していき、脚も長くなっていきました。
しかし、脚は大きな体を支えているわりには細いため、怪我をしやすい部分でもあります。
速く走るために進化した蹄には、血液のポンプ機能もあります。
蹄を地面につけると、蹄が少し広がり、蹄を地面から上げるともとに戻るといった収縮機能があり、これによって脚部の血液循環を助けています。
そのため、蹄は「馬の第二の心臓」と言われています。
蹄を怪我したり、病気にかかってしまったりした場合は血液の循環が上手くいかずに、なかなか治癒せず、ひどいケースでは腐敗して命を落としてしまう可能性もあります。
こういったことから馬の脚や蹄は普段から丁寧に管理をし、少しでも異常があれば速やかに獣医師や装蹄師に相談する必要があります。
骨格

実は、人間と馬の骨格はとてもよく似ています。
二足歩行と四足歩行の違いはありますが、人間の腕と馬の前脚、人間の脚と馬の後脚にはいずれも同じ関節があります。
骨の数もそれぞれ約200個と大きく違いはありません。
そのなかで特に大きく違うのは、蹄の骨。
人間の骨格に当てはめると、馬は中指1本で体重を支えていることになります。
後脚のかかとや膝も人間のものと少し見た目が異なる骨格になっています。
ただし、膝には人間と同じようにお皿もあり、関節の役割自体に大きな違いはありません。
筋肉

筋肉も馬が生き残るための発達を遂げてきました。
走る原動力を生む後脚を動かすお尻や腰の筋肉が発達しています。
また、後脚のパワーをサポートする前脚の付け根にあたる肩も筋肉に包まれています。
また馬は速くかつ長く走れるように赤筋と白筋のバランスがいい動物だと言われています。
赤筋は遅筋とも呼ばれ、持久力に優れた筋肉です。
白筋は速筋とも呼ばれ、瞬発力やスピード、パワーに優れた筋肉です。
この筋肉をバランスよく持つことによって、遠くまで速く走ることができます。
まとめ

今回は馬の体の仕組みや生態についてご紹介しました。
実は、人体についてもまだほんの一部しか分かっていないと言われています。
馬について分かっていることは、もっと少ないはずです。
今後もそれまでの常識がどんどん変わっていくはず。
それでも、馬の体や生態について少しでも知っていれば、仲良くなる手助けになるかもしれません!
このページをシェアする