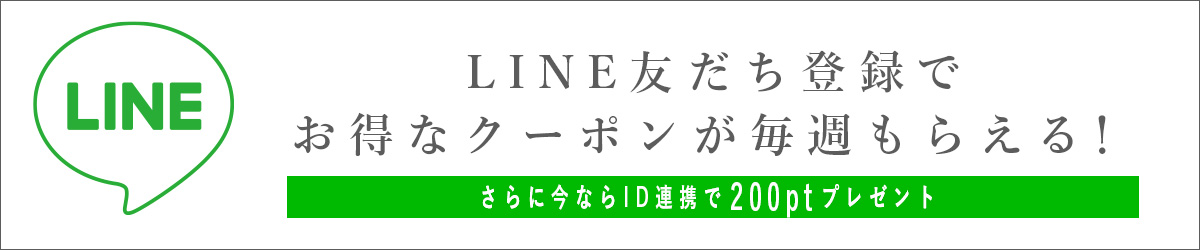馬術(2)【~馬にたずさわる人全てが調教者~103】
前回で騎手が完成していなければならないことは、馬に指示を正確に発動する為の動作をする際にも自身の身体がふらつくことなくバランスの取れた状態のまま、まずはしっかり推進が出来ている事。
さらに坐骨、恥骨、股関節、背筋、肘、脇、拳、膝、ふくらはぎ、踵それぞれ左右バラバラの違った位置で違った動き、違った強さと違ったタイミングで使用できなければなりません。
各部位を1つ1つチェックしていたのでは、訳が解らなくなってしまいます。
そこで自身の構えを①推進②上半身③下半身の3つに分けてイメージすると良いでしょう。
1,推進
前方推進: 上半身を垂直に保ちながら力を丹田に集め、ふくらはぎと踵を馬体に着け何時でも強弱の使い方ができるように保ちます。坐骨を真上から圧迫する為に膝を閉じることなく伸ばすように鐙を踏み下げます。
後方推進: 前方推進と同じ姿勢のまま恥骨を鞍に押し当て両膝をやや後に位置するように下方後方に踏み下げます。
2,上半身
頭のてっぺんから坐骨までを垂直にして肩はネジラナイためにも常に坐骨の上にあるように構えます。
力を抜き背中が丸まらないように肩甲骨を寄せて身体の真横に肩から肘までを垂らすように置きます。
次に、手綱をピント張った時に肘から馬の口までが直線上にあるように肘の角度を決めます。
肘から前は出来るだけ力まずに、拳も手首を折った構えにならないよう手の甲から肘まで平になるように構えます。
動作が入る時だけ握るようにします。
馬の首を左右に向ける為には肘の前後の動きが出来るようにします。
顎を譲らす際には、手の平を上に向けるように使います。
また、進行方向を示す時には進行方向側の拳の手の平をわずかに進行方向に向けます。
3,下半身
両坐骨を均等にして鞍に跨り、股関節と膝、足首各関節が力まないようにして、踵が自身のお尻上のラインにあるように位置し、膝が綺麗なくの字になるように構えます。
この状態で鐙を踏み下げた時、足首がしっかり折れて股関節、膝、足首の各関節の位置が変わることなく真下へ踏み下げている事が重要です。
この状態でふくらはぎを馬体に密着させ脚とバランスの安定を保つようにします。
横幅の狭い馬は、騎乗者の左右のバランスの崩れに弱いので騎手は常に左右のバランスを崩すことなく坐骨の左右違った圧迫の強弱を使い分け出来なければなりません。
左右の脚の位置を変えるのは、片方の脚はそのままの位置で、もう一方の脚は下方後方へ股関節、膝、足首の構えを変えずに明確に変えましょう。
馬に何かを教えると言う事は、望む運動の態勢を馬が最も取りやすい状態で動くことが出来るように仕向ける事で、その動作をする上で馬が少しでも苦しいと感じないで自然発生的に動くようでなければなりません。
望む動作であったら、その動作に気付いてすぐさまオーバーに褒める事が最も大切です。
令和7年4月
長谷川 雄二
このページをシェアする